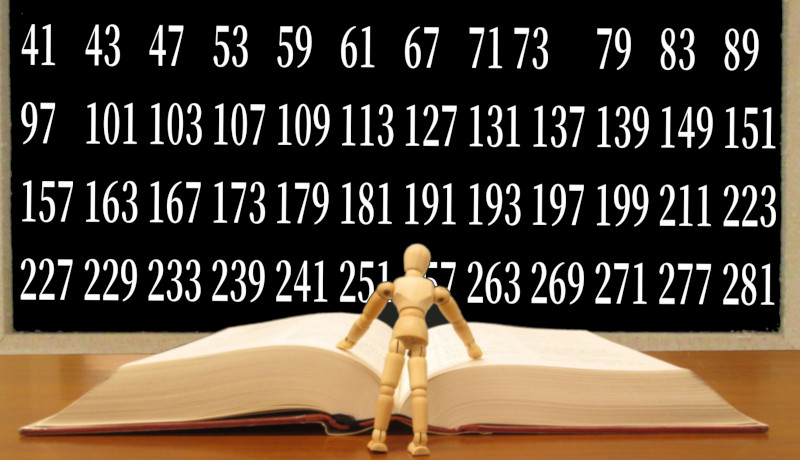
[書評]志村五郎『記憶の切繪図』 我が道を貫いた数学者の回想録
志村五郎(1930-2019)は楕円曲線とモジュラー形式の性質に関する「谷山・志村予想」で知られる世界的な数学者だ。1964~1999年には米国プリンストン大学教授を務めた。一般向けの著作には随筆や数学に関するものの他に、趣味の中国説話文学に関するものもある。
戦時中、独学で数学を学び始める
本書は著者曰く、特に時代の気分を書くことを試みたという回想録である。タイトルは「江戸切繪図」という江戸時代の地図に由来する。尾張徳川家の藩士であった先祖の名前が記してあるのが、今の東京都新宿区の牛込地域だ。
志村氏は3歳から終戦の1945年、15歳までを、その切繪図の範囲内である大久保、高田馬場、早稲田で過ごした。小学校低学年の1937年頃くらいまでを「よい時期だった」と振り返る。姉三人兄一人のあとの末っ子で、何でも自分の好きなようにしようとし、それが世間の通念と違っていることがよくあったそうだ。第四中学校(現・戸山高校)に進学したが、旧式で余裕がないところがいやだった。3年生の11月から勤労動員で働き、空襲に遭って二度も焼け出された。そして、授業を受けられない期間に独学で数学を学んだ。
終戦後に旧制第一高校を経て東京帝国大学を卒業。数学を選んだのは、自分の知識欲を満たすために、そして何かできることがあると思ったからだった。1953年に論文原稿を数学者アンドレ・ヴェイユ(哲学者シモーヌ・ヴェイユの兄)に送って高く評価されたことが転機になった。その後、モジュラー関数体の理論をまとめて共同研究者である谷山豊氏との共著の中に収めた。
アメリカに渡り、世界的な数学者へ
ヴェイユの推薦もあって、志村氏はフランス国立科学研究センターと米国プリンストン高等研究所で短期間働いた。1959年に東京に戻ると、前年の11月に自殺した谷山氏とのやりかけの仕事をまとめ直した。そして1962年、プリンストン大学に客員研究員として赴任した後に、長期に在籍するようになったという。
本書は著者の晩年の手記であるが、それにしても、物事をあいまいにせず率直で、時に辛辣だ。年寄りの無能さと尊大さにはどうしても批判的になると述べているものの、教わる立場でありながら心を閉ざす若者に対しての評価はやはり辛口。また、志村氏本人が数学者としてこうありたいと願っていた姿は、進歩し続けることであり、それができたと自負していた。
1986年のある晩、夫人と二人で食卓に向かい合い、故・谷山氏の話をしていて彼のことがかわいそうでたまらなくなって、二人して向かい合って涙を流したという。これを契機に英文で追悼文を書きあげている。ただ、その一方で、本書の付録三「あの予想」では、谷山氏が1955年に提起した問題は不正確だと断じている。即ち、「谷山・志村予想」と呼ばれているものは、志村が独自にまとめた「志村予想」と呼ぶべきものだということだ。いくら悲惨な死に方をした親友を悼んでいても、それは真理とは無関係だという著者の気概が感じ取れる。
時代を超え、独立した研究姿勢で我が道を貫いてきた世界的数学者の人柄は強烈であり、そして魅力的だ。
『記憶の切繪図』
副題 七十五年の回想
著者:志村五郎
発行日:2008年6月25日
発行:筑摩書房
(冒頭の写真はイメージ)
<関連記事>
【書評】科学者の随筆・評伝 | NEWS SALT(ニュースソルト)

