
スライムの触感を科学的に分析 10m以上伸びるスライムの作成に成功
高エネルギー加速器研究機構(KEK)と総合科学研究機構は8月28日、多摩六都科学館との共同研究で、スライムの触感を科学的にアプロ...
東北大学理学部物理学科修士課程修了。ソフトウェア技術者。情報機器・教育機器の開発に長年従事し、近年は自動車エレクトロニクスやIoTに関わる。得意分野は本業の技術系。絶滅危惧種、環境問題などもカバー範囲。

高エネルギー加速器研究機構(KEK)と総合科学研究機構は8月28日、多摩六都科学館との共同研究で、スライムの触感を科学的にアプロ...

惑星科学者のカール・セーガン(1934-1996)といえば、ベストセラーとなった科学ドキュメンタリー『COSMOS』(1980)...

岡山大学は20日、約21~24億年前に地球の大気に大量に酸素が出現した「大酸化イベント」のメカニズムを解明したと発表した。海水中...

九州大学は8日、クルミの葉から他の植物の生育を抑える物質を新たに発見したと発表した。環境に優しい次世代型のバイオ除草剤としての利...

上智大学は4日、登山計画の情報をAI技術で処理し、登山の事故リスクを予測する手法を開発したと発表した。登山者が事前に事故リスクを...

東京科学大学は7月28日、三菱電機との共同研究で、光触媒パネルを用いてCO2からエネルギー物質であるギ酸を生成させる人工光合成技...

東北大学は24日、製造過程でCO2が排出されない「グリーン水素」の製造において、過電圧を低減することで水電解の効率化に成功したこ...

東京大学は14日、中国石油大学、ENEOS Xplora(東京都千代田区)と共同で、CO2が火成岩の表面と直接反応して瞬時に鉱物...
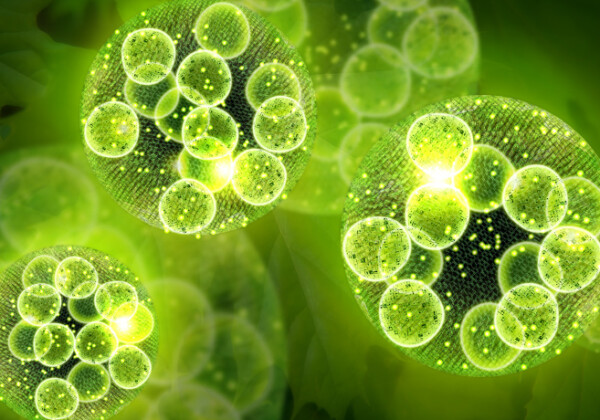
広島大学は4日、バイオ燃料の生産手段として有望視される微細藻類ナンノクロロプシスのオイルの生産性を高める鍵となる物質を発見したと...

東北大学、秋田大学、北海道大学は3日、農業廃棄物のもみ殻と鉱山副産物のパイライトから高耐久な次世代電池用触媒を開発したと発表した...

東北大学と日本原子力開発機構は24日、空気中の水分子を吸着・放出して蓄放熱することが可能な厚さ数nm(ナノメートル;1nm=10...

沖縄科学技術大学院大学(OIST)は19日、オーストラリアのサンシャインコースト大学と共同で、サンゴ礁を食い荒らすオニヒトデが匂...

琉球大学は10日、1998年の大規模白化後に回復した沖縄のサンゴにおいて、異種間交雑が発生しそれが遺伝的多様性を高め、環境変化へ...

東京海洋大学は5月30日、市民科学を利用した、東京湾における希少種のクジラ、スナメリに関する調査によって、その生態の一端が明らか...

千葉大学は5月28日、三井化学と共同でフクロウの翼を模倣したドローンのプロペラを開発し、騒音低減効果を実証したと発表した。都市部...

東京大学は20日、植物の室内栽培において、従来用いられていた発光ダイオード(LED)に代えて赤色レーザーダイオード(LD)を用い...

志村五郎(1930-2019)は楕円曲線とモジュラー形式の性質に関する「谷山・志村予想」で知られる世界的な数学者だ。1964~1...

東京理科大学は7日、CO2排出量を削減し施工の省力化を実現できるコンクリート「ハイプロダクリート」を、東急建設と共同で開発したと...

東北大学は1日、微生物を用いて一酸化二窒素(N2O)を高速に除去する新たなプロセスを開発したと発表した。環境への負荷が低く、廃水...
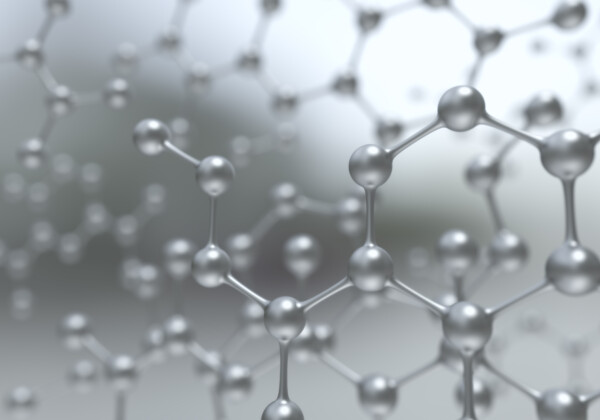
東京大学は22日、バイオマス資源であるセルロースを前処理なしで糖に分解することに成功したことを発表した。効率的なバイオマス変換を...

近畿大学は17日、琵琶湖固有種の魚ホンモロコが産卵場所として選ぶ条件を解明したと発表した。重要な水産資源であるホンモロコの産卵環...
